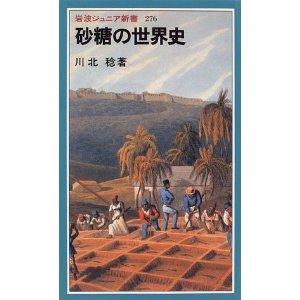戸塚隆将『世界のエリートはなぜ、この基本を大事にするのか?』朝日新聞出版、2013
自己啓発本がはびこるこの世の中で、本書は最もシンプルに書かれた仕事をする上での基本的なテクニック本である。D・カーネギーのように具体例を用いて、哲学的なことを述べるのではなく、組織や社会の中で生きていくための基礎を構築するための考え方が述べてある。
著者はゴールドマン・サックスとマッキンゼーの二社で仕事の経験があり、いわゆるビジネス界のヒエラルキーの頂点近くにいた故に、非常に説得力がある。そうなると、近年はやりの自己啓発本がいくつか頭上に浮かぶ人もいるだろう。しかし、そのようなキャリアポルノなどと囃し立てられるキャリア自慢本ではない。
効率よく、気持ちよく仕事をするためには様々な点に意識する必要があり、それはどのような職種であっても共通する部分がある。「3秒で開ける場所に常にノートを置いておく。」「作った資料は自分の商品だと心得る。」など、どこかで聞いた当たり前のことを再確認させてくれるのが本書である。常に基本を意識するということは、仕事ができる人間への一番の近道なのではないだろうか。